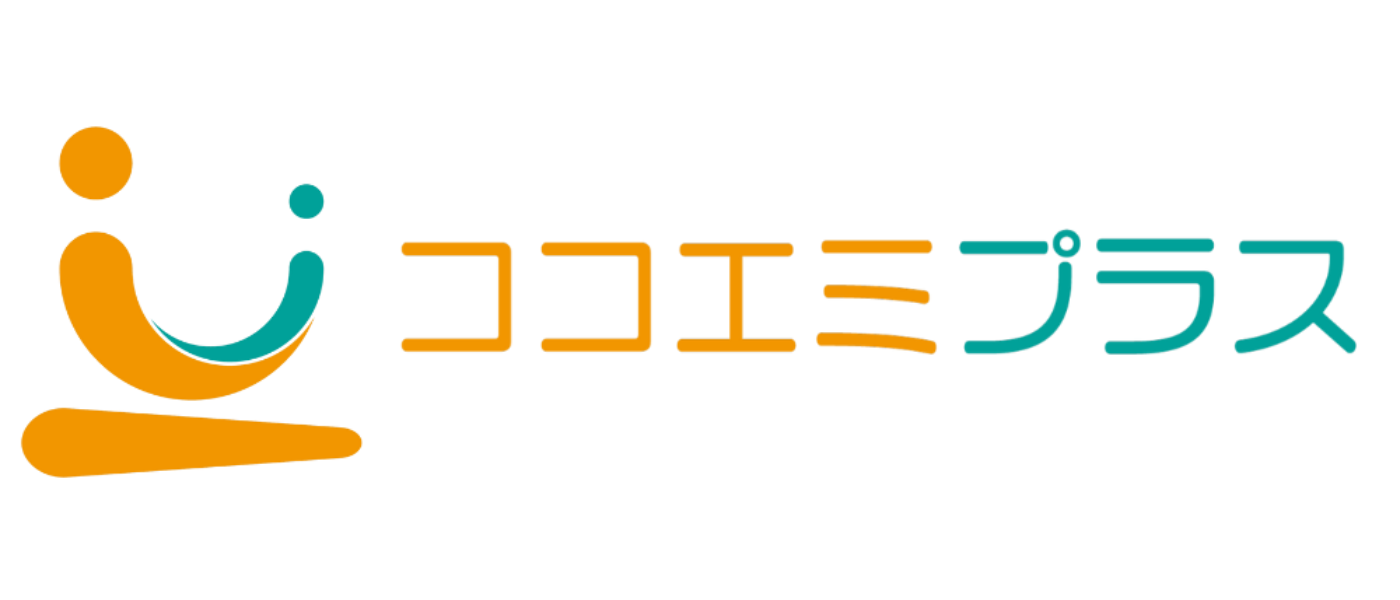「おかんは尼崎のキャバレーでホステスやって、生きるために必死やったんかもしれない。
けど、私はその”必死”に巻き込まれる形で、毎晩のようにボコボコにされてました。」
夜中に酔っぱらって帰ってきては、私を見るなり始まる暴力。
「おのれさえおらんかったら!」
「おのれなんど産まんかったらよかったわ!」
「おのれなんど死んだらええんじゃ!」
その度に、私は体を丸めて、ただ嵐が過ぎるのを待つしかありませんでした。
体中があざだらけになり、夏の暑い日でも長袖ジャージを着て学校へ。
担任の先生が「最近、どないしたんや?」「なんか困ってることないんか?」と心配してくれても、
「なんでもないわ」
「ただ転んだだけや」
そう突っ張り続けるしかなかったんです。
そんなどん底みたいな毎日のある日、母が急に機嫌よく帰ってきて、私の前でにこーって笑って言うんです。
「明日、万博行くで!」
正直、耳を疑いました。
「えっ? どこ行くん?」
思わず聞き直したら、母は私の両手をぎゅっと握りしめて、興奮した声で言いました。
「万博や!大阪万博に二人で行くで!」
あの悪魔みたいな母が、大阪万博?
「ほんまかいな……」って最初は素直に喜べへんかった。
でも、母はもう大はしゃぎで、「あれ見ようや! これも見たいわ!」とか、次の日のプランを楽しそうに話してました。
その姿を見てたら、「嘘ちゃうんやな」「ほんまに行くんやな」って思えてきて、気がついたら私まで飛び跳ねるほど嬉しくなってました。
「やっぱり、おかんは俺のおかんや! 俺のこと嫌ってなんかおらんねん!」
心の中がそう叫んでいました。

万博での一日は、まさに夢のようでした。
母は私の手を離さず、「あれ見ようや!」「これも見たいわ!」と楽しそうに引っ張ってくれる。
帰り道、電車の中でも「ほんまに楽しかったなぁ」「また行けたらええのにな」と笑い合って。
まるで普通の親子のように過ごせた、たった一日でした。
けれど、その2週間後。
母は私の手を引いて、ある建物に連れて行きました。
「ここで待っとき」———それが母の最後の言葉でした。
後から知らないおじさんが入ってきて、こう告げたんです。
「ここは児童養護施設ちゅうところでな。おかんやおとんのいない子らが暮らすとこや。
お前のおかんはもう戻ってこん。今日からここで暮らすんやで」
万博での楽しい記憶が、頭の中から一気に追い出されていく。
どうして? あんなに笑っていた母が、どうして私を置いて行ってしまったんだろう。
まるで底なしの真っ暗闇に、ぽんと落とされた気分でした。
次回は「虐待と捨てられの後に——施設で過ごした日々」について。
なぜ、”兄弟”と呼べる仲間たちと出会えたのか。
そして、その出会いが私の人生をどう変えていったのか。
引き続き、お話ししていきます。